三端子レギュレータは最も身近なICですので、これまでに使ったことのある方も多いと思います。図1に三端子レギュレータのバリエーションを示します。三端子レギュレータは、各メーカーから発売されており、5Vの正電源1A用なら通称は、「7805」ですが、メーカーによって正式名称は「LM7805」であったり、[NJM7805]であったりします。どこのメーカーのものでも同じように使えます。
電圧は一般に、5V,6V,7V,8V,9V,10V,12V,15V,18V,24Vのものが用意されています。
三端子レギュレータの使い方をマスターしよう!
![]() 三端子レギュレータについて
三端子レギュレータについて
三端子レギュレータは最も身近なICですので、これまでに使ったことのある方も多いと思います。図1に三端子レギュレータのバリエーションを示します。三端子レギュレータは、各メーカーから発売されており、5Vの正電源1A用なら通称は、「7805」ですが、メーカーによって正式名称は「LM7805」であったり、[NJM7805]であったりします。どこのメーカーのものでも同じように使えます。
電圧は一般に、5V,6V,7V,8V,9V,10V,12V,15V,18V,24Vのものが用意されています。
 |
| 図1. 三端子レギュレータのバリエーション |
![]() 三端子レギュレータ使用上のノウハウ(1)
三端子レギュレータ使用上のノウハウ(1)
実際に使用する場合には、図2のように入力と出力(なるべくレギュレータの足の近く)に必ず、0.1μF程度の発振防止用コンデンサを入れ、定格値の40%以上の電流を取り出すには、必ず放熱器に取り付けて使用します。
また、最低入力電圧は、「使用レギュレータ電圧+2.5V以上」となるように選びます。入出力間電位差を極端に小さくすると、平滑回路で発生するリプル電圧の谷間でICが動作できなくなり、出力電圧に大きなリプル・ノイズが発生します。ACラインの電圧が−10%〜−15%低下したときに、レギュレータの入出力間電位差が確保されている必要があります。
低消費電力化のため、入出力間電位差をどうしても小さくする必要がある場合には、入出力間電位差が0.2V〜0.5Vでも動作できる、低ドロップ・アウト型のレギュレータを使うようにします。
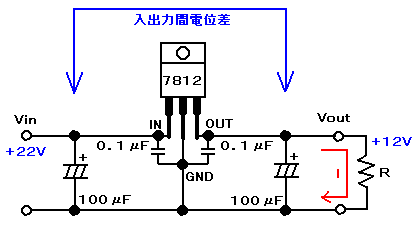 |
| 図2. 三端子レギュレータの使い方(1) |
さて、逆に出力電圧値に対して、あまりに入力電圧が高いと、その差分がロスになるため、発熱が増加しますから注意が必要です。
簡易型の安定化回路を構成する場合には、三端子レギュレータは非常に便利なのですが、取り出し得る電流値について説明します。
規格を見ると、78シリーズのパッケージ(TO−220)で、78○○は最大電流が1A(max)となっていますが、放熱器をつけなければ、例え定格の半分の500mAで使ったとしても壊れることがあります。(^^;)
さて、放熱器なしの場合の許容損失PD(max)は、式(1)のようになります。
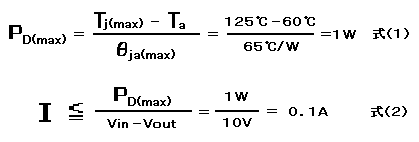
ここで、Tj(max)は、最大ジャンクション温度で125℃、Taは最大周囲温度で65℃とします。θja(max)は放熱器無しの熱抵抗で、TO−220パッケージでは65℃/Wです。
仮に、図2のように入力電圧Vin=22Vを、7812を使用してVout=12Vの出力電圧を得るものとします。Vin−Vout=10Vが入出力間電位差になります。
このとき、取り出せる最大電流 I は、式(2)のようになります。最大1A取り出せるICがなんと、0.1Aしか流せません。そんなのウソつきだ!なんて思わないで下さい。データシートにもウソは書いていません。よく誤解している人がいますが、負荷電流はIC設計上の電流であって、許容消費電力とは無関係なのです。
そうすると、IC内部のジャンクション温度の上昇を抑えて、許容消費電力をアップさせることが必要になってきます。すなわち、発生した熱を外気に逃がすため、放熱フィンが必要になってくるわけです。
![]() 三端子レギュレータに放熱器をつけよう!
三端子レギュレータに放熱器をつけよう!
放熱器の放熱能力を表す単位に放熱器の熱抵抗θsaがあり、単位は℃/Wです。たとえば、θsa=6.7℃/W(リョーサン製P45L30)の放熱板に、TO−220パッケージの三端子レギュレータを実装すると、最大許容損失は、式(3)のようになります。
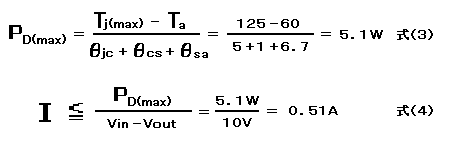
ここで、θjcはIC内部と外周器までの熱抵抗で、およそ5℃/Wくらいです。θcsは外周器と放熱器までの熱抵抗で、シリコンゴムやマイカ(雲母)板を使って絶縁するときに生じます。
ここで、入出力間電位差を先ほどと同じく10Vとすれば、最大負荷電流は式(4)となり、放熱器無しの場合と比べて、大きな電流が取り出せるようになります。
熱抵抗の小さな(放熱面積が大きい)放熱器を使用することが得策ですが、コスト的な面で金属ケース(アルミケースが良い)にレギュレータICを取り付ければ、ケースが放熱器の役目を十分してくれます。
![]() 三端子レギュレータ使用上のノウハウ(2)
三端子レギュレータ使用上のノウハウ(2)
+5Vのロジック回路電源を、図3のように本来のアナログ電源から流用したい場合がよくあります。この場合には、入出力間電位差が大きくなってしまうため、ロジック回路で使える電流値が小さくなってしまいます。
もし、負荷電流 I が分かっていれば、三端子レギュレータ(7805)の入力に抵抗Rを付けて、電圧ドロップを作ると良いでしょう。図3の例では、入力電圧Vin=22Vが抵抗の電圧ドロップにより、三端子レギュレータ7805の入力電圧は、10Vになっています。三端子レギュレータの発熱は抑えられますが、その代わり抵抗にて発熱を処理する必要があります。
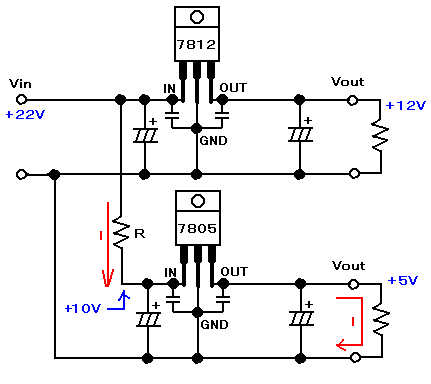 |
| 図3.三端子レギュレータの使い方(2) |
![]() 三端子レギュレータ使用上のノウハウ(3)
三端子レギュレータ使用上のノウハウ(3)
入手しやすい三端子レギュレータの出力電圧は、5V,6V,8V,12V,15V,18V,24Vで、これ以外の電圧を選るには、図4、図5のような電圧ブーストの方法があります。知っていると、何かの役に立つでしょう。
図4では、抵抗R2に流す電流IRは、ブーストした電圧Voutに関係しないように、なるべく大きな電流を流します。IRと三端子レギュレータ自身の消費電流IQを加算した電流を抵抗R1に流し、R1(IR+IQ)なる電圧を発生させます。
7815を用いて17Vの出力電圧を得るには、IQ≒5mA,IR=(5〜10)IQを設定し、
R2=VREG/IR=15V/25mA=600Ω
R1=(Vout−VREG)/(IQ−IR)=66Ω
として定数を求められます。
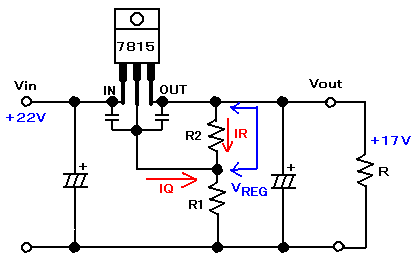 |
| 図4.三端子レギュレータの電圧を可変する方法(1) |
図5は、三端子レギュレータのGND端子に、ダイオードD1,D2を挿入する方法です。出力電圧は約13.2Vとなります。
ダイオードの順方向電圧として、VF=約0.6Vが電圧ブーストされます。2個であれば2×VF=1.2Vが電圧ブーストされます。ただし、ダイオードのVFは温度係数として、約−2.2mV/℃ですので、温度により変動することをご承知下さい。
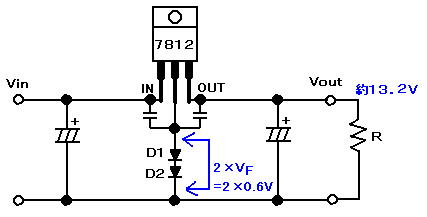 |
| 図5.三端子レギュレータの電圧を可変する方法(2) |
 |
|
 |